確定申告の時期が近づいてまいりました。
2025年提出・令和6年分の確定申告については、定額減税の影響もあり、若干の変更点があります。

本記事では、その変更点も踏まえて令和6年分確定申告書第『第三表』の見方や書き方について詳しく解説するとともに、税額計算の流れや控除の種類も紹介いたします。
確定申告書の種類
所得税の確定申告書には第一表・第二表・第三表・第四表の4種類の用紙があります。
第一表と第二表は、確定申告をする全員が提出しなければなりません。
第三表は申告分離課税の対象となる所得がある人が、第四表は損失の申告をする人が、それぞれ提出します。
- 第一表:収入や所得、所得控除、税額控除などの金額を記入
- 第二表:所得の内訳や所得控除に関する事項など、第一表で記載した事項の詳細な内容を記入
- 第三表:株式等の譲渡所得や不動産の譲渡所得など、分離課税の対象となる所得について記入
- 第四表:純損失の金額や雑損失の金額を翌年以降に繰り越す場合などに記入
確定申告書の用紙は国税庁のサイトからダウンロードでき、税務署に行って確定申告書の用紙をもらうこともできます。
この中でも今回は損失が出た場合に、その損失を翌年以降に繰り越し節税したい場合に作成する『第四表』についての見方や書き方をみていきましょう。
損失申告とは?
損失申告とは、事業で損失が出た場合にその損失分を繰り越すための申告のことです。
損失分を繰越すことで、次年度以降に利益が出た場合に、損失分を利益から差し引くことができ節税につながります。
なので次の場合には損失申告をすることがおススメです。
- 所得金額が赤字の場合
- 所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる場合
- 所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる場合
損失申告をする場合には、確定申告書の第一表と第二表だけではなく、第四表の提出も必要となります。
続いてはその確定申告書第四表の見方と書き方をみていきましょう。
確定申告書 第四表の見方と書き方
確定申告書第四表は下記のようになります。
(引用元:国税庁「申告書第一表・第四表【令和6年分以降用】」©国税庁)
それでは第四表の見方、書き方をブロックごとに解説します。
ⅰ. 損失額又は所得金額
損失額又は所得金額欄については、所得ごとに参照する書類が変わってくるので、所得の区分に応じてみていきましょう。
A:「経常所得」の欄
A「経常所得(68)」には、確定申告書 第一表の①から⑥までの合計額に、⑩の金額を足した金額を記入します。
下記の場合だと第一表の①事業所得5,367,200+③不動産所得1,279,200+④利子所得0円+⑤配当所得80,000+⑥給与所得1,264,000+⑩雑所得0=8,008,400円
第三表「経常所得(68)」には上記合計8,008,400円を記入します。
B:「譲渡・一時」の欄
Bの「譲渡(70)、(72)」欄、「一時(73)」欄については総合課税なので、確定申告書第二表の総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項をみながら作成します。
(引用元:国税庁「申告書第一表・第四表【令和6年分以降用】」©国税庁)
Bの「譲渡(69)、(71)」欄については、分離課税なので、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地建物用】をみながら作成します。
(引用元:令和6年分譲渡所得の申告のしかた©国税庁)
譲渡所得の確定申告について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

C:「山林」の欄
C:「山林(74)」の欄は、山林所得収支内訳書(計算明細書)をみながら作成します。


D:「退職」の欄
D:「退職(75)」の欄は、退職所得の源泉徴収票などをもとに作成しましょう。
「一般」には一般退職手当等、「短期」には短期退職手当等、「特定役員」には特定役員退職手当等に関する事項を記入します。
Ⓐ収入金額欄
退職所得の収入金額の合計額(税込)を記入します。
Ⓑ必要経費等欄
退職所得控除額を以下の計算式で求めて記入します:
勤続年数が20年までの場合: 40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円)
勤続年数が20年を超える場合: 70万円×勤続年数−600万円
※ 障害者となったことにより退職した場合は、100万円を加算します。
Ⓒ差引金額(Ⓐ−Ⓑ)欄
Ⓐ収入金額からⒷ必要経費等を差し引いた金額を記入します。
Ⓔ損失額又は所得金額欄
退職手当等の種類によって以下のように計算します。
- 一般退職手当等のみ: Ⓒ差引金額×0.5(赤字の場合は0)
- 短期退職手当等のみ(Ⓒ差引金額が300万円以下): Ⓒ差引金額×0.5(赤字の場合は0)
- 短期退職手当等のみ(Ⓒ差引金額が300万円超): Ⓒ差引金額−150万円
- 特定役員退職手当等のみ: Ⓒ差引金額(赤字の場合は0)
E:「一般株式等の譲渡・上場株式等の譲渡・上場株式等の配当等」の欄
E:「一般株式等の譲渡・上場株式等の譲渡・上場株式等の配当等」の欄については、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書をみながら該当箇所を記載します。


(引用元:国税庁HP「令和6年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた」©国税庁)
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など株式譲渡関係の申告書の作成の仕方はこちらの記事をご覧ください。

ⅱ. 損益の通算
「損益の通算」では、「損失額又は所得金額」の(68)から(75)の金額を転記します。
ただし、「分離譲渡71」は「1 損失額又は所得金額」の金額が黒字なら転記不要です。
ⅲ. 翌年以後に繰り越す損失額
翌年以後に繰り越す損失額があるなら、該当欄に金額を記入します。
「青色申告者の損失の金額(83)」は、青色申告をしている人で、「損失額又は所得金額の合計額(82)」の中に(71)欄の特定損失額に係る純損失(特定純損失)がある人が計算して記入します。
計算方法は、以下「(83)欄の計算式」記載の手順に従ってAから順番に算出し、Gの金額の先頭に△を付けて「青色申告者の損失の金額(83)」に記入します。
【(83)欄の計算式】
| A | (82)欄の金額 |
|---|---|
| B | 確定申告書 第一表の①と②欄の合計額(黒字のときは0) |
| C | 確定申告書 第一表の③欄の金額(黒字のときは0) |
| D | 確定申告書 第四表の「損失額又は所得金額」の「ス」と「ソ」欄の赤字の合計額 |
| E | 確定申告書 第四表の「損益の通算」の(74)欄の金額(黒字のときは0) |
| F | B+C+D+E |
| G | AとFのいずれか少ない方の金額 |
ⅳ. 繰越損失を差し引く計算
「繰越損失を差し引く計算」には、前年から繰り越した損失の金額と、確定申告をする年分から差し引く損失、翌年に繰り越す損失の金額を記入します。
2以上の年分に生じた損失がある場合は、最も古い年分に生じた損失から順次差し引きます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は損失が発生した場合に作成する「確定申告書-第四表」の見方・書き方についてみていきました。
基本的にすでに作成している他の申告書から転記するかたちですが、いろんなところから拾ってくる必要があるため、少し難しかったですね。
関連して、全員が提出する必要のある『第一表』『第二表』についても知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。


この記事が皆様の確定申告のお役に立てば幸いです。
それでは、また!
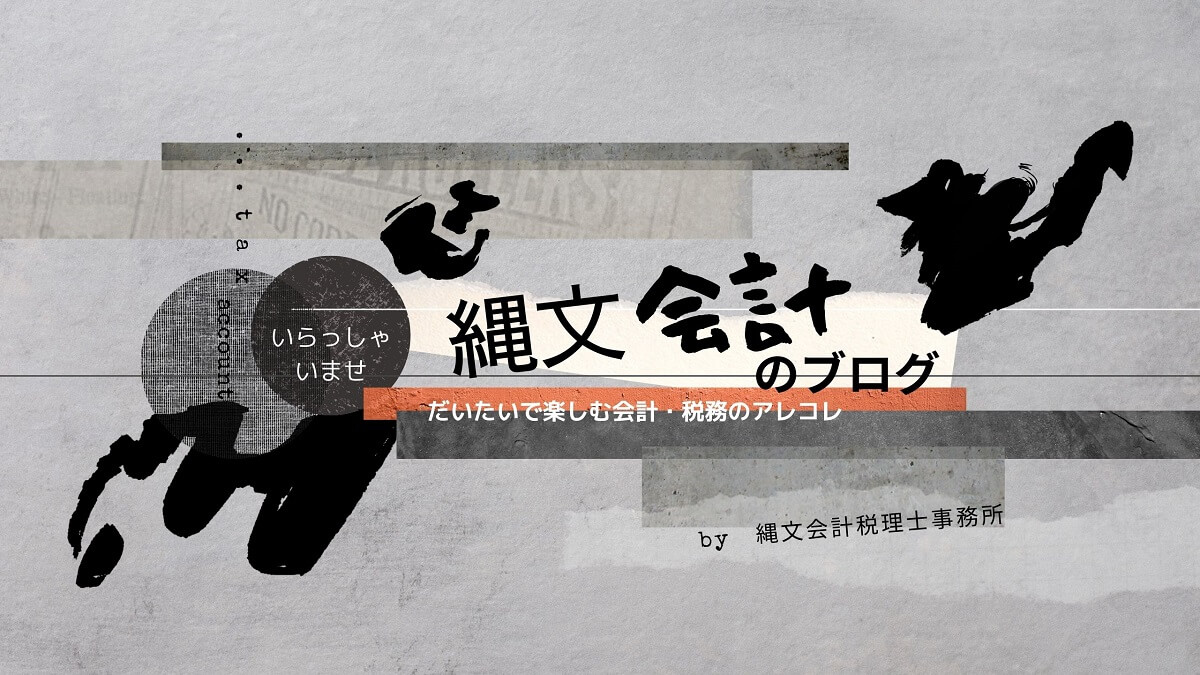















コメント