ご質問をいただきました。

近年はどの企業も人手不足が深刻です。優秀な人材を確保する目的で、採用決定者へ入社支度金や転居費用を支給することも増えてきました。
今回は入社支度金や転居費用を負担した場合の税務処理や会計処理についてみていきましょう。
まずは入社支度金からです。
1.採用決定者への入社支度金の税務処理と会計処理
それでは早速、入社支度金の税務処理と会計処理からみていきましょう。
入社支度金はその支給時期によって、所得税法の考え方が変わります。
会社側の処理においても、どの所得税に該当するかで、
- 源泉徴収をすべきかどうか?
が変わってきますので、まずは所得税の扱いを見ていきましょう。
①入社支度金の所得税法上の考え方
採用決定者への入社支度金については、入社支度金という名の通り、「雇用契約」を前提としています。
なので「労務の対価」としての性質を有していると考えられます。
また、支度金ですので、一時的に受け取るものですが、一時所得には「労務の対価」としての性質を有するものは含まれないことから、入社支度金は一時所得には該当しません。
また、転居等に関係なく支給されるものですから、「転居費用として通常必要と認められる金額」に該当するかどうかも定かではないため、非課税所得にはなりえません。
そのため、支払われるのが入社前か入社後なのかによって以下の2つが考えられます。
入社前に支払われる入社支度金
入社前に支払われる入社支度金は、契約金と考えられるので「雑所得」とします。
(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
204-29 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、役務の提供の対価が給与等とされる者が当該役務の提供契約を締結するに際して支払を受ける契約金も含まれる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)(注) 上記の契約金は、雑所得(35-1の(9)参照)となり、法第2条第1項第24号《定義》に規定する臨時所得に該当する場合があることに留意する。
(引用元:国税庁HP『契約金(第7号関係)』©国税庁)
また、入社前であれば、労務の提供が行われる前ですので、源泉徴収が必要です。
源泉徴収額は以下の通りとなります。
- 100万円以下 → 支給額×10.21%
- 100万円超 → 100万円以下部分×10.21% + 超過部分×20.42%
入社後に支払われる入社支度金
入社後に支払われる入社支度金は、賞与と考えられるので「給与所得」とします。
入社後の場合は、すでに労務の提供が行われているので、その実態に応じて、賞与として給与所得と判断します。
源泉徴収額も賞与の場合に応じて処理しましょう。
②入社支度金の消費税法上の考え方
入社支度金の消費税については、一律支給される支度金については、「通常必要とされる部分の金額」とはいえず、実費弁済の性質を有していないことから、「課税仕入れ」に該当しません。
ただし、他社の従業員を引き抜くためのいわゆる「引抜料」については、対価性を有するものとして、「課税仕入れ」に該当します。
③入社支度金の法人税法上の考え方・会計処理
「採用教育費」または「福利厚生費」等として、支出時に経費(損金)計上することとなります。
2.採用決定者への転居費用の会計処理と税務処理
続いて転居費用についてみていきましょう。
①転居費用の所得税法上の考え方
転居費用については、次の非課税要件を両方とも満たす場合は「非課税」となり、源泉徴収は不要となります。
- 支度金と転居費用が明確に区分されていること
- 金額が「通常必要と認められる範囲」内であること
どちらか一方でも満たさない場合は、
- 転居費用が支度金に含まれる場合 → 全額が入社前は「雑所得」扱い、入社後は「給与所得」で課税
- 通常必要額を超える部分 → 超えた分を入社前は「雑所得」、入社後は「給与所得」として課税
となり、源泉徴収が必要となります。
②転居費用の消費税法上の考え方
転居費用として支給される金銭が、
- 実費相当額であり、
- 実際に支払った経費の金額を超えない額で精算を行う精算実費弁済の性質を持つ場合
の2つの要件を満たす場合は、消費税の「課税仕入れ」として扱われます。
一方、一律に支給される入社支度金など、実費弁済の性質を持たないものは、課税仕入れとしては扱われません。
③転居費用の法人税法上の考え方・会計処理
「採用教育費」または「福利厚生費」等として、支出時に経費(損金)計上することとなります。
転居費用の注意点
転居費用は、非課税要件である、
- 支度金と転居費用が明確に区分されていること
- 金額が「通常必要と認められる範囲」内であること
の2要件をクリアすることで、税法上の有利な恩恵を受けられます。
そのために下記の点に注意しましょう。
注意点①:支度金と転居費用を明確に区分
支度金と転居費用を明確に区分することが必要です。
そのために、支給明細書の内訳を明確に区分して作成するようにしましょう。
注意点②:転居費用の「通常必要額」の基準は?
通常必要額については、社内規則に定めておくのが安全です。
社内規則により、転居による移動距離などを考慮して支度金額を決定するように定めましょう。その際、支給額と実費弁済相当額が同額程度となるように定めます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
ここまで、入社支度金・転居費用の税務処理と会計処理について、まとめました。
かなり内容が複雑でしたね。
一つの処理から所得税法・消費税法・法人税法を考慮しないといけないのは大変だと思います。
だけど、対応できればスーパー経理マンです!
難易度は高い処理だと思いますが、これを機に内容を整理していただければと思います。
この記事がバックオフィスで働く皆さんのお役に立てば幸いです。
そして、今後も税務・会計に役立つ記事を発信していきますので、またお越しいただければ嬉しいです。
それでは、また!
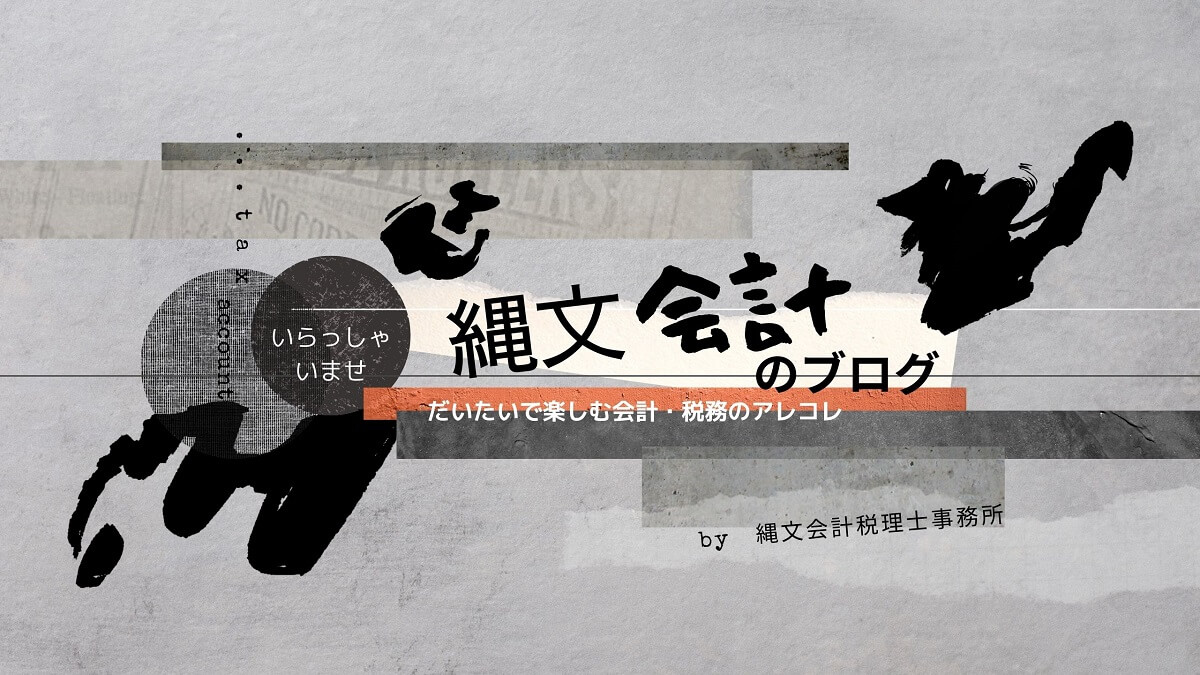


コメント